- j k l -
| JAGUAR | 乽A Vision乿 |
 |
慜擭偺倀俲僗僷乕僋擭娫傪庴偗偨俋俉擭丄婜懸偺怴恖偲偟偰榖戣傪廤傔偨儘儞僪儞偼JAGUAR偺僨價儏乕嶌偱偁傞丅僒僂儞僪偼崪懢僊僞乕儘僢僋丄摼堄側僥儞億偼儈僪儖僥儞億丄儃乕僇儖傕拞掅壒偵嫮偔僟儖僀姶偠偺惡偑偐偭偙傛偄丅偑丄婥偵側傞丅嶌昳偲偟偰偍傕偟傠傒偑側偄丅埆偔偼側偄丄掱搙偺姶憐偵側偭偰偟傑偆丅桪廏側怴恖偺嶌昳偵偼墲乆偵偟偰偙偺傛偆側嶌昳偑偁傞丅幚椡偼偁傝儊儘僨傿傕昞尰椡傕偁傞偺偵嶌昳偲偟偰幐攕偟偰偟傑偆丅偦傟偼峔惉椡偱偁偭偨傝丄嬋偺娚媫偩偭偨傝偲僩乕僞儖揑側僾儘僨儏乕僗姶妎偑昁梫偲偝傟傞傫偩偗偳丄偙傟偑側偐側偐擄偟偄丅偄偄嬋偑彂偗傞僀僐乕儖偄偄傾儖僶儉偑嶌傟傞丄傢偗偱偼側偄傫偩側丅傑偀偦傟偱傕僆傾僔僗傒偨偄偵妝嬋偑埑搢揑偩偲栤戣側偐偭偨傝偡傞傫偩偗偳丄偦偙傑偱偺愢摼椡偵寚偗傞丅妝嬋偵偦偖傢側偄傛偆側丄廔傢傝偩偲偐嬻偭傐偩偲偐偄偆壧帉偑傗偨傜懡偔丄柧擔傊偺揥朷傪岅偭偨傝偲偦偺悽奅娤偼旕忢偵撪徣揑偱埫偄傕偺偩偭偨傝偡傞偟丅偆乕傫丒丒丒丅傑偀偦傟偱傕嬋扨埵偵栚傪岦偗傞偲杮摉偵偐偭偙偄偄嬋偼壗嬋傕偁傝丄嘆乽Up And Down乿傗嘋乽Coming Alive乿偁偨傝偼傗偽偄傛儂儞僩丅 |
| JET | 乽Get Born乿 |
 |
僆乕僗僩儔儕傾敪丄偄傑傗慡悽奅偱攏幁攧傟偺JET偺僨價儏乕嶌丅偙偆偄偆戝墹摴儘僢僋儞儘乕儖偑僀僊儕僗傗傾儊儕僇偱偼側偔僆乕僗僩儔儕傾偲偄偆抧偐傜旘傃弌偟偰偒偨偺偵偼嬃偒丅媰偔巕傕梮傝偩偡栥愨儕僼偺嘇乽Are You Gonna Be My Girl乿廂榐丅偲偵偐偔儘僢僋儞儘乕儖偲偼偙傟偩偤両偲尵傢傫偽偐傝偺儌儘捈媴宯偱丄僈儗乕僕棳峴埖偄偝傟傞晽挭偑偁傞拞丄偦偺捈媴傇傝偺埑搢揑側愢摼椡偱偦傟傪挼偹彍偗偨姶偼偁傞丅嫹偄僗僥乕僕偐傜峀偄奐偗偨僗僥乕僕傑偱懳墳偱偒傞妝嬋偺憉夣偝偲丄儃乕僇儖偑俁恖偄傞僗僞僀儖偑晲婍偩傠偆丅嘋乽Lool What You've Done乿傗嘐乽Move On乿傪戙昞偵丄傾儖僶儉偺敿暘偑僶儔乕僪側偺偩偑丄懠偺僶儞僪偲堦慄傪夋偟偨偺偼僶儞僪偺報徾偲柕弬偡傞傛偆偩偗偳丄傗偭傁傝僶儔乕僪傊偺幏拝丄側偺偩傠偆丅嬋傪暦偐偣傞偙偲偺弌棃傞僶儞僪偼傗偼傝嫮偄偲偄偆偙偲偩丅偦偟偰偙偺僶儞僪偼僪儔儅乕偑堦斣偐偭偙偄偄丅僆儗偑僪儔儉傪傗偭偰偄傞偣偄偐丄尒偨栚傕墘憈傕懙偭偰崅昡壙傪弌偣傞僪儔儅乕偼側偐側偐偄側偄傫偩偗偳丄偙偺僶儞僪偺僪儔儅乕丄僋儕僗丒僙僗僞乕偼惁偔岲偒偩側丅嘇偺俹倁偺僋儕僗偲偐傓偪傖偔偪傖偐偭偙傛偄丅 |
| THE JESUS AND MARY CHAIN | 乽Psycho Candy乿 |
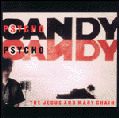 |
俉侽擭戙慜敿丄儕乕僪孼掜偵傛傝寢惉偝傟偨僕僓儊儕丄俀侽擭慜偺嶌昳偲偼偲偰傕巚偊側偄俉俆擭敪昞偺侾st丅僾儔僀儅儖僗僋儕乕儉偺儃價乕偑僪儔儅乕偲偟偰嵼愋偟偰偄偨帪婜偺桞堦偺嶌昳偱傕偁傞丅傑偀僪儔儉偼暿偵僕僓儊儕偵偲偭偰偼偁傑傝廳梫偱偼側偄丅僊僞乕偺偨傔偺偍慥棫偰偩丄埆偔尵偊偽丅偝偰丄僕僓儊儕偱偁傞丅尰嵼悢懡偺僼僅儘儚乕偑偄傞儅僀僽儔傗僺僋僔乕僘偱偁傞偑丄偦偺斵傜偵嫮偔塭嬁傪梌偊偨僶儞僪偱偁傞丅摿昅偡傋偒偼僒僀働側儊儘僨傿偺棤偱柭傝嬁偔婼偺僨傿僗僩乕僔儑儞僊僞乕丄偙傟偵恠偒傞丅嘇乽The Living End乿丄嘊乽Taste The Door乿丄嘐乽In A Hole乿丄嘔乽Inside Me乿偁偨傝偺僲僀僘偼懱偵僓僋僓僋撍偒巋偝偭偰偒偦偆側傎偳攋夡揑偱偁傞丅偟偐偟儊儘僨傿偺桪夒偝傕懳徠揑偵栚棫偮傕偺偱偁傝丄俇侽擭戙傾儊儕僇偺壒妝偵塭嬁傪庴偗偰偄偦偆側丄嘍乽Cut Dead乿丄嘕乽Sowing Seeds乿偺億僢僾僱僗偝偵偼巚傢偢帹傪孹偗偰偟傑偆丅攋夡揑偱偁傝桪夒揑丄偳偪傜偐傪帩偭偰偄傞僶儞僪偲偄偆偺偼偦偺僶儞僪偑椙偄埆偄偵娭傢傜偢悢懡偔偄傞傕偺偱偁傞丅偟偐偟偙偺椉嬌抂偵偁傝偑偪側僼儗乕僘傪暪偣帩偭偰偄偨斵傜偩偐傜偙偦崱尰嵼偵偍偗傞巟帩偲昡壙傪摼偰偄傞偙偲偼尵偆傑偱傕側偄丅 |
| KEANE | 乽Hopes And Fears乿 |
 |
枅擭枅擭擭巒偵偼奺壒妝帍偑乽嵟嫮偺怴恖両両乿塢乆暲傋棫偰傞傕偺偱丄偍傑偊傜偺拞偱嵟嫮偺怴恖偭偰偺偼堦懱壗慻偄傞傫偩偲撍偭崬傒偨偔側傞傕傫偩偑丄斵傜偼偦偺拞偱傕僩僢僾僋儔僗偺晹椶偺惉岟傪廂傔偨偲偄偊傞偩傠偆丅弶搊応慡塸侾埵偲偄偆夣嫇傪惉偟悑偘偨彇忣攈僉乕儞偺僨價儏乕嶌丅彇忣攈偲偄偭偰傕丄僋儕僗丒儅乕僥傿儞偑帩偮挘傝媗傔偨乽堿乿側旤偟偝偲偼懳嬌偵偁傞乽梲乿側妝嬋丄偐偲偄偭偰僼儔儞丒僸乕儕乕偑帩偮帺屓傪尒偮傔傞傛偆側桪偟偄抔偐偝偲傕傑偨堘偆丄柧傞偝偲婓朷傪慺捈偵奜偵墴偟弌偟偨桇摦姶堨傟傞嶌昳丅僊僞乕傕儀乕僗傕偄側偄偲偄偆摿堎側僶儞僪僗僞僀儖傪帩偪丄摿偵偍傕偟傠偄傾儗儞僕傪偡傞傢偗偱傕側偔扺乆偲崗傓尞斦偲僪儔儉偑幚偵偆傑偔嶌梡偟偰偄偰丄壧偺弮悎側晹暘傪尒帠偵堷偒弌偟偰偄傞傫偩側丅嘆乽Somewhere Only We Know乿偼戝柤嬋丄昁挳丅堦悽戙慜偺傾僀僪儖偑懢偭偰偟傑偭偨傛偆側僟僒偄儃乕僇儖偱偁傞偑丄壧彞椡偲昞尰椡偼偡偽傜偟偔崅偔丄傑偀儔僀僽偱偼側偔俠俢傪挳偔僶儞僪偐側丅僉乕儃乕僪偼儔僀僽偱偺抏偒曽惁偔偐偭偙偄偄偗偳偹丅
|
| THE KILLS | 乽Keep On Your Mean Side乿 |
 |
償傿償傿偺儃乕僇儖挻偐偭偙偄偄両彈儃乕僇儖偵"偐偭偙偄偄"側傫偰宍梕帉傪摉偰傞側傫偰偁傫傑柍偄偩偗偵偆傟偟偄恖偨偪偑搊応偟偰偔傟傑偟偨丅儃價乕丒僊儗僗僺乕戝愨巀偱僾儔僀儅儖僘偺慜嵗偵傕敳揊偝傟偨僉儖僘侾st丅傾儊儕僇撿晹偺搚廘偄僽儖乕僕乕偝偲丄俈侽擭戙僷儞僋偵偍偗傞撍敪偝傪暪偣帩偮傛偆側偦偺扨弮側傛偆偱怺偄妝嬋忋偱丄儂僥儖偺懢偔嫢朶揑側僊僞乕儕僼偑挳偒庤傪偖偄偖偄偖偄偖偄堷偒崬傫偱偄偔丅偦偟偰忋婰偟偨偑壗偲尵偭偰傕帪偵愨嫨偟丄帪偵梔墣偵敆傞償傿償傿偺儃乕僇儖僗僞僀儖偑丄偐偭偙偄偄彈偲偼偙偆偄偆傕傫偩偤偲偄偆婥偵偝偣傞丅傾償傽儞僊儍儖僪側彈儃乕僇儖僗僞僀儖偲偄偆偲NY偺YEAH YEAH YEAHS偁偨傝偑偄偰丄幚嵺堷偒崌偄偵弌偝傟偨傝偟偰偄傞偗偳拞恎偼慡慠堘偆偟傚丅斵傜傛傝傕偭偲抧偵崻傪偼偭偨傛偆側壒妝娤傪帩偭偰偄偰丄偁偔傑偱壒妝惈偼夁嫀偺孈傝婲偙偟偲嵞峔惉偵揙偟偰偄傞丅偱偒偦偆偱側偐側偐偱偒側偄偙偲側傫偩偗偳丄帺暘偨偪偼偳偆偡傞偲堦斣偐偭偙傛偔側傞偐丄偦傟傪偙偺恖偨偪偼偟偭偐傝棟夝偟偰偄傞丅僉儖僘傪抦傜側偄恖偼偲傝偁偊偢僔儞僌儖嬋偵傕側偭偰傞嘇乽Cat Claw乿傗嘍乽Fried My Little Brains乿傪挳偄偰丄偦偺僟乕僋側悽奅偱傇偭旘傫偱梸偟偄丅 |
| KINGS OF LEON | 乽Youth And Young Manhood乿 |
 |
偼偠傔僔儞僌儖傪帇挳偟偨帪偵丄偁偀傑偨偙偺庤偺僈儗乕僕宯偐丄偲巚偭偰偨偄偟偰暦偐偢偵棳偟偰偟傑偭偨傫偱偡丅偩偭偰偙偺崰偭偰儂儞僩偵僈儗乕僕傪弌偣偽偄偄傒偨偄側晽挭偱偝丄僈儗乕僕偑岲偒偩偐傜偙偦丄傕偆傗傔偰揑側姶偠偩偭偨傫偱偡丅偱丄屻擔斵傜偺幨恀傪尒偰徴寕傪庴偗偨丅暯嬒擭楊俀侽嵨偲偄偆偦偺巔偼丄1960擭戙偺傾儊儕僇偐傜僞僀儉僗儕僢僾偟偰偒偨拞擭偺偍偭偝傫偲偟偐巚偊側偄弌偱棫偪偱偁傝丄偦傟傪尒偨弖娫帇挳婡偵懍峌丄側傞傎偳両偲歑傝傑偟偨丅偝偰丄孼掜亄廬孼掜偺偙偺僨價儏乕嶌丄傑偩庒偄傫偩偐傜懍偄嬋傪傗傞偺偝丄偲杮恖払偑岞尵偟偰偄傞捠傝丄堄奜偵傕僄儌乕僔儑僫儖側巇忋偑傝偲側偭偰偄傞丅僇儗僽偺揇廘偄惡傕丄偍偭偝傫惡偑戝岲偒側僆儗偲偟偰偼僶僢僠儕偩偟丄偦偺憱傞儕僘儉偵僶僢僉儞僶僢僉儞偺懯栚僊僞乕傕儊儘僨傿偺椙偝偲尒偨栚偱僇僶乕偱偒偰偄傞偐傜椙偟丅偲偵偐偔嘆乽Red Morning Light乿偺儃乕僇儖偺擖傝偺偲偙傠偼幚偵僋乕儖偱丄側傫偲傕徫偄偑偙傒忋偘偰偟傑偆丅慡嬋捠偟偰椙嬋偧傠偄側傫偩偗偳丄傑偀壒傊偺姶妎傪傕偭偲杹偐側偄偲僟儊偩偲巚偄傑偡丅偦偺傊傫偼師嶌傊偺婜懸偲偡傞偐側丅 |
| KULA SHAKER | 乽K乿 |
 |
偆偁乕丄偐偭偙傛偡偓両両僊僞乕偺僇僢僥傿儞僌丄儚僂偺嫮楏側崅梘姶丄僌儖乕償姶敳孮偺儕僘儉戉両僋儕僗僺傾儞丒儈儖僘偺尒偨栚偲偼堘偭偰懢偄惡傕椙偄偟丄堦搙偼傑傞偲敳偗弌偣側偄拞撆惈偁傝丅怴恖僶儞僪偺僨價儏乕嶌偲偟偰偼娧榎偝偊昚偆暥嬪偺偮偗傛偆偺側偄撪梕丅僕儍働偐傜傕傢偐傞偲偍傝丄嘋乽Govinda乿偱摿偵尠挊偱偁傞偑丄柉懓妝婍傪庢傝擖傟偨僀儞僪揑側暤埻婥偑慡曇偵昚偭偰偄偰丄側傫偲傕僒僀働側傾儖僶儉偱偁傞丅摿偵愗側偄僉乕儃乕僪偑報徾揑側嘑乽Tattva乿偼僒僀働姶敳孮丅偟偐偟梫強梫強偼嘆乽Hey Dude乿丄嘍乽Smart Dogs乿丄嘔乽Grateful When You're Dead乿側偳偺崪懢儘僢僋僠儏乕儞偱偟傔偰偄傞偺偱丄娫墑傃傕偣偢偒偭偪傝嵟屻傑偱暦偐偣偰杮崙偱俀侽侽枩枃丄擔杮偱偡傜俆侽枩枃傪攧傞戝僸僢僩僙乕儖僗偲側傞丅擔杮偱俆侽枩梞妝偑攧傞偭偰寢峔偁傝偊側偄丄偲偄偆偐丅惁偄丅僕儈僿儞傪闂闇偲偝偣傞傛偆側僊僞乕儕僼傗偦偺恈偺捠偭偨壒嶌傝摍僊僞乕儚乕僋偑杮摉偵慺惏傜偟偔丄儖僢僋僗椙偟堢偪椙偟惡椙偟墘憈椙偟丄偲揤偼擇暔傕嶰暔傕梌偊偨傕偆偨傢偗偱偡丅偪側傒偵傾儖僶儉僞僀僩儖偺K偼丄偼偠傔偼僶儞僪柤偩偭偨傫偩偲丅俋俁擭偵儈儖僘偝傫偑僀儞僪偺帥偱塭嬁傪庴偗偰嬋嶌傝傪巒傔偨嵺偵丄僀儞僪壒妝傗帉偵孾栔偺怺偐偭偨屆戙僀儞僪峜掗偺柤慜偵偪側傫偱偮偗傜傟偨偺偑僶儞僪柤僋乕儔僔僃僀僇乕側偺偩偲丅傫傑偀偲偵偐偔暦偒傑偟傚偆丄楌巎揑柤斦偺堦枃偱偡丅 |
| THE LA'S | 乽The La's乿 |
 |
俋侽擭偵偙偺嶌昳偺傒傪敪昞偟夝嶶偟偰偟傑偭偨儕乕丒儊僀償傽乕僗棪偄傞儔乕僘丅俋侽擭戙僽儕僢僩億僢僾惃偼娫堘偄側偔偙偺儔乕僘偺嬋偵塭嬁傪庴偗偰偄偰丄偦傟儔乕僘偺恀帡偠傖傫丄偰嬋傕偪傜傎傜丅尰嵼偵偍偗傞恖婥倀俲僶儞僪偵傕塭嬁偼梌偊偰偍傝丄儕僶僥傿乕儞僘偺儊儘傗丄僐乕儔儖偺僼儘儞僩儅儞丄僕僃乕儉僗丒僗働儕乕偺儃乕僇儖僗僞僀儖偼偙偺儔乕僘偁偭偰偺傕偺偩偲尵偭偰椙偄偩傠偆丅偨偭偨堦嶌昳偱偙偙傑偱昡壙傪庴偗揱愢壔偟偰偟傑偭偨揰偵偍偄偰丄儔乕僘傪抦傜側偔偲傕丄偄偐偵偙偺嶌昳偑慺惏傜偟偄傕偺偱偁傞偐傪憐憸偡傞偺偼擄偔偼側偄偼偢偩丅儕乕丒儊僀償傽乕僗偺朼偓偩偡儊儘僨傿偲帪偵廰偔帪偵憉傗偐側惡偵偼儈儏乕僕僔儍儞偲偟偰偺嵥妎偑堨傟偰偄傞丅傑偨丄旕忢偵寉夣偱僙儞僗偁傞儕僘儉姶妎傪儊儞僶乕慡堳偑帩偪崌傢偣偰偄傞揰傕尒摝偣側偄丅慺惏傜偟偄儊儘僨傿偵僕儍僉僕儍僉偟偰儕僘儈僇儖側妝婍戉丄嘇乽I Can't Sleep乿丄嘊乽Timeless Melody乿丄嘍乽There She Goes乿丄嘑乽Feelin'乿傪昅摢偵億僢僾偱椙幙側嬋偑僘儔儕偲暲傇丅摿偵儔乕僘嵟戝偺柤嬋偲偺屇傃惡崅偄嘍偺儊儘僨傿偵偼棴懅偑楻傟傞丅傑偨丄偲偁傞応偱丄偙偺嘍偵搊応偟偰偔傞pulls my train偲偄偆晹暘偼丄懳栿偩偲晛捠偵乽斵彈偑杔偺揹幵傪堷偔乿偲栿偝傟偰偄傞偑丄幚偼乽悶傪堷偔乿偲偄偆堄偱丄偙傟偼斵彈偲暿傟偨垼偟傒偺壧偱偼側偔丄巰傫偱偟傑偭偨柡偵憐偄傪抷偣傞壧側偺偩乮悶傪堷偔埵攚偑掅偄乯丄偲偄偆夝庍偑偁偭偨丅偩偲偟偨傜両偙偺嬋偼挻愨傕偺偩偲巚偄傑偣傫偐丅偱傕妋偐偵偙偺嶌昳拞丄嘍偩偗儌儘側儔僽僜儞僌偲偄偆偺傕夝偣側偐偭偨偐傜側乕丄偦偆側偺偐傕偟傟側偄側丅揤嵥偩側丄儕乕丒儊僀償傽乕僗偼丅壗傗偭偰傫偩傠崱丅 |
| THE LIBERTINES | 乽Up The Bracket乿 |
 |
堦弖偱傕偭偰偐傟傞嵟崅偺弖娫偑偄偨傞偲偙傠偵懚嵼偡傞嶌昳丅僼儘儞僩儅儞偱偁傞僊僞乕仌儃乕僇儖偺僺乕僞乕偲僇乕儖偺桭忣偲丄扤傕偑帺桼偵曢傜偣傞棟憐嫿傪嫟偵栚巜偡偲偄偆惥偄偐傜巒傑偭偨偙偺僶儞僪丄側傫偲傕僒僀僪僗僩乕儕乕偐傜枺椡揑側攜偨偪偱丄庰偲栻偵傑傒傟攧弔廻偵揮偑傝崬傫偩傝嬻偒壠偵晄朄懾嵼偟側偑傜屳偄傪攍傝崌偄擣傔崌偄側偑傜擔乆忔傝墇偊偰偒偨丄偺偩偲丅偲偵偐偔僼儘儞僩擇恖偺帪偵娒偔丄帪偵姶忣攳偒弌偟側壧偄偭傉傝偑惁傑偠偔丄変愭偵偲嫞偄崌偆傛偆偵丄傑偨巟偊崌偆傛偆偵儊僀儞儃乕僇儖傪岎屳偵壧偆條偼尒偰偄偰挳偄偰偄偰怱桇傞丅抏偗偰側偄偠傖傫両側僿儘僿儘僊僞乕傗峳嶍傝偡偓傞偦偺僒僂儞僪傕丄偆傑偄偲偐僿僞偲偐偦偆偄偆傕偺傪墇偊偨晹暘偱偺儘僢僋儞儘乕儖傪柭傝嬁偐偣偰偄傞偺偱仢丅偁傑傝偵傕儕傾儖偱愒棁乆偵惛恄柺傗惗妶柺傪揻偒弌偟偨壧帉偼僊儕僊儕偺晹暘偱惉傝棫偭偰偍傝丄僨價儏乕僔儞僌儖嘗乽What A Waster乿偼憗懍偦偺撪梕偐傜曻憲嬛巭丅偲傑偀枺椡傪弴偵嫇偘偰偄傞偑丄僆儗偑儕僶僥傿乕儞僘傪戝岲偒側堦斣偺棟桼偼丄偦偺儊儘僨傿偺慺惏傜偟偝偱偁傞丅僀僊儕僗摿桳偺僔僯僇儖偱棳傟傞傛偆側儊儘僨傿偑偳偺嬋偵傕枮嵹偱偁傝丄嘆乽Vertigo乿偺僒價屻丄嘇乽Death On Stairs乿丄嘋乽Time For Heroes乿偺俙儊儘丄嘑昞戣嬋乽Up The Bracket乿偺慡曇丄嘊乽Horrorshow乿丄嘓乽The Boy Looked At Johnny乿丄嘖乽I Get Along乿偺僒價丅丒丒丒偆乕傫丄偪傚偭偲庤曻偟偱梍傔偡偓偨偐側丅 |
| THE LIBERTINES | 乽The Libertines乿 |
 |
偙偙傑偱慜嶌偲堘偆嶌昳偵側偭偰偟傑偆偲偼丅偼偭偒傝尵偭偰慜嶌偺傛偆側帺怣偲惃偄偵枮偪堨傟偨儕僶僥傿乕儞僘偼偙偙偵偼側偄丅偁傞偺偼丄晄埨丄幐朷丄愗側偝丄偦偟偰偡偑傝偮偔婓朷丅偲傫偱傕側偔埆偄榐壒忬嫷丅偦傟偼僪儔僢僌栤戣偐傜敪惗偟偨僺乕僞乕偲僇乕儖偺徴撍偵傛傝僶儞僪撪忬懺偑朏偟偔側偄偐傜偱偁傝丄僶儞僪傪敳偗偰偄偨僺乕僞乕偑傢偢偐擇廡娫偩偗栠偭偰偒偨偦偺堦弖傪巊偭偰堦婥偵榐壒偟偨偲偄偆嶌昳偱偁傞偐傜偩丅偲偵偐偔壒偑埆偔偦偟偰枹姰惉傕偄偄偲偙傠側妝嬋孮丄儊儘僨傿傕掕偐偱偼側偄愡傕偁傞丅儕僶僥傿乕儞僘偲偄偆乽僶儞僪乿帺懱傪垽偟偰偄傞傢偗偱偼側偄恖偑丄偙偺嶌昳偩偗暦偄偨傜乽側傫偠傖偙傝傖乿偲側傞偺偼娫堘偄側偄丅偟偐偟丄偙偺僑儈嶌昳傪柤嶌偨傜偟傔傞棟桼偼偢偽傝乽儕傾儖乿偝偱偁傞丅忬嫷偵嬯栥偡傞僺乕僞乕丄僇乕儖椉巵偺姶忣偑傕傠偵揻業偝傟偰偄傞丅偦傟偼旂擏側偙偲偵杮摉偵慺惏傜偟偄垼廌偲儘儅儞僠僘儉堨傟傞儊儘僨傿偲屳偄傪垽偟斱壓偡傞壧帉傪嶌傝弌偟偰偟傑偭偨丅嘆乽Can't Stand Me Now乿偱偺丄乽偍傑偊偼壌傪嫋偟偰偔傟側偄乿傪岎屳偵壧偆條偵丄儘僢僋偺儕傾儖偝傪姶偠側偄搝偼巰偵偨傑偊丅壌傪傢偐偭偰偔傟側偄丄嫋偟偰偔傟偲壧偆僺乕僞乕偲丄壌偼偍傑偊傪嫋偟偰偄傞偲壧偆僇乕儖丅壧帉偱媰偗傞丅偦偙偵偁傞偺偼娫堘偄側偔儕傾儖偝偱偁傝恀偺儘僢僋儞儘乕儖偱偁傝僷儞僋偱偁傞丅偦偟偰僆儗偼丄乽庤傪偮側偛偆傛惵弔偩偤僆僀両僆僀両僆僀両乿偲偄偆搝傜偑帺暘偨偪偺偙偲傪乽僷儞僋乿偲屇傇偺偑梋寁偵嫋偣側偔側傞偺偱偁傞丅 |
| LONGWAVE | 乽The Strangest Things乿 |
 |
僗僩儘乕僋僗偲偺僣傾乕偱偺偡偽傜偟偄儔僀僽偵傛傝堦婥偵偦偺柤傪崅傔偨儘儞僌僂僃乕償偱偡丅弌壒偺堦壒傪暦偗偽偦傟偱傕偆幚椡偺崅偝傪偆偐偑偄抦傞偙偲偑偱偒傞丅偙偙傑偱僀僊儕僗偺壒傪柭傜偡偙偲偺偱偒傞傾儊儕僇僶儞僪傕捒偟偄丅杮恖払傕朷傫偱偄偨丄嬻娫偺杺弍巘僨僀償丒僼儕僢僪儅儞偵傛傞僾儘僨儏乕僗傪庴偗偨摪乆偺僨價儏乕嶌丅柧傜偐偵儅僀僽儔揑側旕忢偵鉟楉偱桪夒側壒傪柭傜偡嘆乽Wake Me When It's Over乿偺傛偆側僊僞乕偑傗偼傝拲栚偳偙傠丅偐偲偄偊偽僗僺儕僠儏傾儔僀僘僪偁偨傝偑傗偭偰偒偦偆側憇戝側晜梀姶揑嘍乽Meet Me At The Bottom乿傒偨偄側嬋傕偁傞丅儖乕僩壒傪壓偘偰偄偔儀乕僗偵忔傞僊僞乕偺媰偐偣嬶崌偑慺惏傜偟偄丅僉儍僢僠乕側嬋傛傝傕帺暘払偺岲偒側偙偲傪傗偭偰傞報徾偺嬋偺曽偑偼傞偐偵弌棃偑椙偔丄嘆丄嘋乽I Know It's Coming Someday乿丄嘍丄嘑乽Tidal Wave乿丄嘒乽The Ghosts Around You乿偑岲偒丅墘憈傕偟偭偐傝偟偰傞偟丄儃乕僇儖傕拞掅壒偵廳傒傪帩偮椙儃乕僇儖丅儔僀僽傾僋僩傕偲偰傕椙偐偭偨偺偱丄旕忢偵桪摍惗揑側嶌昳偱偡丅備偊偵傕偆傂偲屄惈傎偟偄偲偙傠丅惁偔嬉戲偱僴乕僪儖崅偄擸傒側傫偩偗偳丄偙傟偩偭偨傜儅僀僽儔丄儗僨傿僆僿僢僪丄僗僺儕僠儏傾儔僀僘僪暦偔側偀丄偭偰姶偠丅偩偐傜傕偆傂偲屄惈両偦傟偱敳偒傫偱偰傎偟偄丅偱偒傞偲巚偆偐傜丅 |